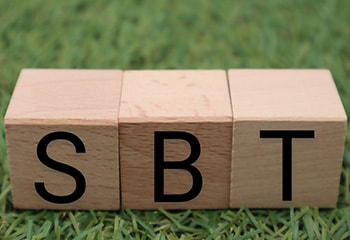ノンファーム型接続で広がるFIT制度の可能性
更新日時:2020.12.25

「FIT」とは、2030年度までに再エネ比率を22~24%まで拡大することを目的として2012年7月に始まった再生可能エネルギー固定価格買取制度です。対象となるのは「太陽光」「風力」「水力」「地熱」「バイオマス」の5つのいずれかから発電した電気で、電力事業者が買い取ります。電力事業者が再生可能エネルギーを買い取るための費用は一般の電力使用者から再エネ賦課金として徴収され、運営されています。再エネ賦課金は再エネの導入につれ上昇傾向となっており、国民負担の軽減が課題となっています。また、省エネを実施するなど一定の条件を満たすことで再エネ賦課金の減免を受けることができます。
FIT制度が始まって以来、太陽光発電を中心に再生可能エネルギーが普及し、2010年度から7.9%上昇し、2018年度16.9%になりました。しかし、目標の22~24%にはまだ届いておらず、さらなる再エネの導入が必要です。
| (kW) | 導入水準 (2019年9月) |
FIT前導入量 (2019年9月) |
ミックス (2030年度) |
ミックスに対する導入進捗率 |
|---|---|---|---|---|
| 太陽光 | 5,240万 | 7,760万 | 6,400万 | 約82% |
| 風力 | 390万 | 990万 | 1000万 | 約39% |
| 地熱 | 59万 | 62万 | 140~155万 | 約40% |
| 中小水力 | 980万 | 990万 | 1,090~1,170万 | 約86% |
| バイオマス | 420万 | 1,080万 | 602~728万 | 約63% |
導入の課題となっている1つは電力系統の容量不足です。電力系統の容量不足とは再エネを導入したいが、電力網の設備である変電所などの能力が不足し、発電所を建設できない状況が全国で発生しています。容量不足を解決するには電力網を増強が必要で、多額の費用と時間がかかり、大きなハードルとなっていました。そこで、この問題を解決する手法として考えられているのがノンファーム型接続というものです。これまでの系統容量の検討は接続されている発電所がフル稼働していることを想定し、系統接続容量が検討されてきました。しかし、実際は太陽光などの天候に左右される発電所の状況や需要によって、空き容量が存在する時間があります。この空き容量を利用して空き容量のある時間は売電し、空き容量がない場合は出力を抑制することを合意することで接続が可能な場合があります。これがノンファーム型接続と呼ばれています。出力の指示はインターネット経由で電力会社から情報があり、この情報をもって発電所の出力を制御します。
今まで、空き容量がなく、再エネの導入が進まなかった地域でも今後、再エネの導入が進んでいく1つのきっかけになりそうです。
FIT制度は2022年度より大きな転換点を迎えるとの情報もあり、今後の状況を注視していくことが必要です。
ヤンマーエネルギーシステムではバイオマス発電に力を入れ、再エネ普及に取り組んでいます。また、様々な省エネ機器も取り扱っており、再エネ賦課金減免など省エネが必要なお客様へ最適な提案をいたします。
お気軽にお問い合わせください
ご不明点、ご要望等ございましたらお気軽にお問い合わせください。