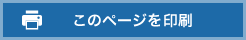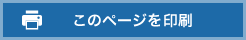助成先一覧
<研究テーマ>
循環水耕液のサンゴ砂礫浄化と蛍光ストレスモニタリングを用いた持続的システムの開発
- 研究の概要
- 水害に見舞われた茨城県常総市内の農家において、水害後の有機物腐敗臭がする地下水に、農水産廃棄物を原料とする有機液肥を混入し、溶液栽培用の培養液として利用、濾過・浄化機能が期待できるサンゴ砂礫を栽培培地として用いる「サンゴ砂礫農法」で培養液の腐敗を軽減する方法を研究する。
さらに、循環・濃縮された培養液による作物の塩ストレスなどを、トマト根からの分泌物質を指標として検知する「ストレスモニタリング法」についても研究する。
- 研究者 :
- 明治大学農学部農芸化学科 中林 和重 准教授
- 助成期間:
- 2016年4月1日~2017年3月31日
- 助成額 :
- 70万円
研究の成果についてうかがいました
- Q1:完了報告書の「今後の予定」に記載された、「サンゴ砂礫・溶液栽培法の養液土耕法への適用」については実施できましたか?
-
助成研究として実施した常総市水害被災農家での「サンゴ砂礫栽培試験」を終えたのち、熊本県水害支援を「サンゴ砂礫の養液土耕法への適用」として取組みました。研究方針を溶液栽培から養液土耕栽培へ切り替えたのには2つの理由があります。
- 熊本のような水害常習地域では高価な溶液栽培設備を導入しても設備二次被害が予想されるため、安価な溶液土耕栽培の方が実用的である。
- サンゴ砂礫溶液栽培を取り止めた施設(北斗市雪害支援)でのサンゴ砂礫の廃棄方法として、ただ畑地に無造作に撒き処分するのではなく、サンゴ砂礫の有効利用について苦慮した。
- Q2:助成研究で得られた成果は、現在の研究活動にどういった形で活かされていますか?
-
常総市洪水跡地の汚れた地下水を用いても、サンゴ砂礫栽培法では水耕栽培よりもミニトマト収量で1.4倍、果実糖度で1.1倍と優れたため、研究方針を蛍光モニタリングからサンゴ砂礫の養液土耕栽培システムへの適用に重点を移しました。この成果は生態工学会2018年次大会発表論文集で報告しました。
さらに2021年度は熊本洪水跡地(水田土)を用いた「養液土耕栽培におけるサンゴ砂礫の有無および肥料の違いがミニトマトの収量や品質に及ぼす影響」について、2021年6月に開催された年次大会で報告しました。
(2021年7月ヒアリング)
- >助成研究のその後 一覧に戻る