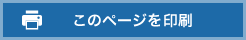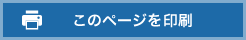助成先一覧
<研究テーマ>
海産魚種苗生産における生物餌料自動培養・給餌装置の開発に関する研究
- 研究の概要
- 従来、海産仔稚魚の種苗生産は、初期餌料生物としてワムシやアルテミアを顕微鏡下目視で計数し、適量を与えるという非常に労力を要する作業だった。本研究では、効率化を図るためのワムシおよびアルテミアを自動で給餌する装置を開発すると同時に、先に開発したワムシ自動培養装置で自動培養を行うだけでなく、自動培養装置内で物質の収支を完全に制御し、長期間にわたって好適環境を維持することができるシステムの構築を目指す。
- 研究者 :
- 東京海洋大学海洋生物資源学科 遠藤 雅人 助教
- 助成期間:
- 2016年4月1日~2017年3月31日
- 助成額 :
- 200万円
研究の成果についてうかがいました
- Q1:完了報告書の「今後の予定」に記載されている、未達に終わった自動pH制御によるワムシ培養およびワムシ、アルテミア自動培養装置を用いた種苗生産システムの開発と、映像解析やデータ通信を得意とする企業と連携した、種苗生産の一般化とIT化は実現しましたか?
-
自動pH制御によるワムシ培養については、80Lの自動培養装置を用いて、異なる4つのpH環境下(pH5.5・6.0・6.5・7.0)で常時運転を行い、間引き運転を行いました。その結果、ワムシの収穫量はpH6.0調整区で最大となり、約8,800万個体/日が回収でき、pHの自動制御設定がワムシ生産の最適化に有効であることが実証されました。一方ワムシ、アルテミアの自動給餌装置を用いた種苗生産につきましては未達となっています。
- Q2:助成研究で得られた成果は、現在の研究活動にどういった形で活かされていますか?
-
本研究で得られた成果は、一部の検討課題について次ステップでの研究の基盤データになっており、自動pH制御によるワムシ培養等に引き継がれています。また、ワムシ自動培養装置に搭載されている個体数を計数する画像解析装置は、単独での使用が可能で、「培養環境の変化がワムシの行動に与える影響」などの調査に利用されています。
ワムシ、アルテミア自動培養装置を用いた種苗生産は未達ですが、本開発よりも先に行うべき周辺の関連研究を進めており、新規に比較的大型の予算に応募し、海産魚種苗生産の自動化を進めたいと考えています。
(2021年7月ヒアリング)
- >助成研究のその後 一覧に戻る