野口伸
1961年北海道三笠市生。北海道大学大学院 農学研究院 教授。専門は農業情報工学、農業ロボット工学。内閣府戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)「次世代農林水産業創造技術」プログラムディレクター。日本学術会議連携会員、日本生物環境工学会理事長。
※取材者の所属会社・部門・肩書等は取材当時のものです。
2017.06.22

アニメやSFで見かけていたロボットが、暮らしの中でも身近な存在になりつつあります。自動車や家電など私たちの身近な分野でもロボットの研究が進み、目にする機会が増えてきました。NEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術開発機構)によれば、日本国内のロボット産業市場規模は、2015年の1.6兆円に対し2020年には2.9兆円、2035年には9.7兆円と大きく成長していくと予想されています。
これら急速な広がりの背景には、技術の進化はもちろんのこと、ロボットによる解決が期待されている社会問題があります。人口の増減や気候変動による食料難、労働力不足などは世界共通の課題。国内に目を向ければ少子高齢化も加わり、ヤンマーが深く関わる農業も同様の課題を抱えています。
果たしてロボットは私たちの暮らしをどのように変えてくれるのでしょうか? 今回はその中でも農業ロボットに注目。第一人者である北海道大学大学院 農学研究院の野口伸教授にお話をうかがいました。農業ロボット研究の過去から現在、そして未来につながるお話を、2回にわたってたっぷりとお届けします。

野口伸
1961年北海道三笠市生。北海道大学大学院 農学研究院 教授。専門は農業情報工学、農業ロボット工学。内閣府戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)「次世代農林水産業創造技術」プログラムディレクター。日本学術会議連携会員、日本生物環境工学会理事長。
※取材者の所属会社・部門・肩書等は取材当時のものです。

野口教授は北海道に生まれ、高校卒業までは山口県で過ごし、北海道大学農学部への進学とともに帰道。農業工学を専攻し、博士課程ではバイオマス燃料を研究されていました。農業ロボットの分野で研究を始めたのは、同大学助手時代の1992年のこと。当時はまさに、農業ロボット研究の黎明期でした。
――野口教授がロボットの研究を始められたきっかけは何ですか?

今から約25年前、私が農業ロボットの研究に着手した時期には、農業における人手不足・労働力不足という課題がすでに顕在化していました。北海道大学では農業が直面する課題が間近にあり、課題解決のために「無人農業ロボットが有効でないか」という発想に至りました。
当初は研究もほとんど進んでおらず、「生研機構基礎技術研究部(現在:農研機構生物系特定産業技術研究支援センター、以下「農研機構」)」が国内で唯一、農業向けの自律走行車両の研究を行っていました。私もそこに交流研究員として所属して、研究開発プロジェクトに参加しました。
――25年前から研究をされているのですね。当時の様子をうかがえますか?

1992年ごろ、私と大学院生らでつくった無人機の1号機は、タイヤから金属板、エンジンまで廃材を集めて自分たちで組み立てました。走るのが精一杯でしたが、1号機からいろんなデータを集めて論文を書きました。本格的な農業ロボットに着手したのは、1995年。トラクター型の2号機を入手してからでしたね。
遡れば1987〜8年には、京都大学が中心となって収穫用ロボットの開発を始めていました。当時農業ロボットというとトマトやイチゴなどの収穫用ロボットが主流でしたが、北海道の農業は大規模な露地栽培が基本です。だからこそ、我々は無人で作業することに目をつけられたんですね。

――研究を開始したころから、いずれこの技術は必要不可欠なものになるだろうという確信は持たれていましたか?

確信は持っていましたね。開発で一番難しかったのは、無人機の位置測定と認識。当時のGPSは精度が低く、価格が高かったので、自前で位置測定システムを開発しなければいけなかったんです。しかし1997年に米・イリノイ大学での実験に参加し、同地でGPSを使った自然環境下での自律走行が高精度で行われるのを目にして、「これはいけるな」と思いました。当然、自律走行に必要となるGPSやGIS(地理情報システム)などの基盤技術の発展が欠かせなかったのですが、この事実が示すように我々の分野だけでは成り立たない研究なのは今も変わりません。
――農業人口が減る中で、一人当たりの面積が増えて大規模化が進む。無人機が果たす役割は大きくなりますね。

そのとおりです。水田農家は今、たいてい一人当たり12ヘクタール、家族二人で20ヘクタールの規模ですが、家族あたり30〜40ヘクタールくらいまで面積を広げていく。担い手の問題と経済性の両面で大規模化が進み、作業効率と収益を上げるために、必要となってくるのが農業ロボットです。
――無人トラクターは実証実験も進み、いよいよ市販化のフェーズです。

ヤンマーさんとも一緒に研究開発した無人トラクターは、コンピュータ制御可能で、GPS受信機を搭載したトラクターを利用した自動走行システムです。タブレットなどであらかじめ設定したコースを走らせながら、耕うん、種まきから収穫まで、すべての作業を無人で行うところまできています。
完全無人化にはいくつかのハードルがあり、まずは実用化を目指すために、有人機と無人機の随伴型のシステムを実現しました。端的にいえば何かが起きた時に人が責任を取れるので、実用化も可能と。ただこの時点でも単純に作業領域が拡大できますし、2台の作業分担で生産性は十分に上がるでしょう。
――市場投入の反響が楽しみですね。現時点での課題はありますか?

価格と安全性ですね。価格の面では、20年前には2000万円くらいだったGPSの値段が下がり、2020年には10万円台も予想される時代になりました。技術の進化とともにより多くの方が手にしやすくなっていくでしょう。
しかし、安全性については単純に技術で解決できる問題ではありません。人工物である限りゼロリスクは不可能ですし、誰でも入れるほ場で無人機が作業するのは、どれほど安全性を高めても100%とは言えないのです。たとえば、背の高い作物の影で子どもが遊んでいたとしたら、画像処理での認識は難しいでしょう。安全性の問題は、技術だけで解決しようとするとコストがかかりすぎるんです。農林水産省が策定した「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン」 では、目視で監視できるところに人がいることが定められています。随伴型はその解決策のひとつです。

農林水産省のデータ によると、日本の農業就業人口のうち65%が65歳以上、平均年齢は66.8歳と高齢化は深刻です。同省は、農機の自動走行について2018年までにほ場内での自動走行システムの市販化、そして2020年までに遠隔監視での無人システム実現を目標として設定。産官学が連携して技術開発が進められています。
――農業ロボットの行く末は、どのような状態を目指すのでしょうか?

政府も、2020年に遠隔監視での無人システムの実現することを目標として設定しています。ただ、さきほどのガイドラインは「道路ではロボット農機を走行させない」と定めているので、畑と畑が離れている場合に非常に非効率。道路交通法の見直しも必要になるでしょうね。
――たしかに働き方が変わる以上、社会の仕組みを変えていく必要もありますよね。農業ロボットの労働力以外の価値についてはどのようにお考えですか?

基本的な役割としては、労働力を代替して人手不足を補うことですが、副次的には生産現場の情報化も期待されています。たとえば、作物の生産現場のデータ化。これまでも農家では手書きの日報をつけたり、管理する動きがあるにはあるのですが、データ化となると全然。頼みは一人ひとりの経験と勘といった状況です。
こうなると労働力不足以上に、高齢化とともに熟練の農家の知恵が消えて行くことが深刻な問題です。継承できずに知恵が失われると、効率が下がり、人は減っていくのに単位面積あたりの収量は落ちる。非効率な負のサイクルに陥ってしまうでしょう。
あと10年経つと今65歳の人は75歳。農業従事者一人ひとりが言語化せずに経験として持っている“暗黙知”を、収集・管理して“形式知”にしていく作業が必要だと考えています。
――生産現場の情報化について、具体的にはどのようなロボットが役立つのでしょうか?

空から無人機を用いるのが一つ。ドローンやヘリを使い、上空からほ場をセンシング/撮影し、生育の悪いエリアや収量のバラつきなどを把握し、データに基づいて農地を精密に管理できるようになります。これはヤンマーさんでも取り組まれてますね 。
なんと言ってもビッグデータとロボットは非常に親和性が高い。こういった作業で得られたほ場や作業のデータは、農家が使うのももちろんですが、無人で作業するロボットの次のステップとして、“農業を知るロボット”という段階が考えられます。ロボット自体がデータを吸収し、成長して、作業にまで反映させる。
――まさに、農業ロボットが人工知能を持って成長していくようなイメージですね。

そう。さらに言えば、こうした新しい技術の導入に興味を持つ、若い新規就農者が増える可能性もありますね。日々学生を前にして、実感もあります。
20年ほど前には、「無人機が実用化したら仕事がなくなる」と農家に言われたこともありますが、ロボットにできる作業を任せることで、人間は人間にしかできない仕事ができるようになる。「何を栽培して、どこに売るか」「何に加工するか」など、農家の人たちがクリエイティブな仕事をする時間ができるという意味でも、ロボットが役に立つと思います。

――農業の課題は国により様々です。すでに実用化されている、あるいは研究されている最新のロボットについて、国外の技術も含めて野口教授の目線で紹介いただけませんか?

大規模農業の本場・欧米諸国を筆頭に、中国や韓国、アジア諸国も研究を進めています。人手不足という意味では、欧米は日本ほど深刻ではありませんが、農業就業人口はどの国でも減少しています。
それよりも食糧難が心配されています。国際連合食糧農業機関(FAO)の予測では、2050年に世界の総人口は96億人に達し、この人口を養うためには食糧生産を2倍に引き上げる必要があるというんですね。今のままでは、確実に食糧が足りなくなります。
もうひとつの課題は、気候変動によって雨の少ない地方でもゲリラ豪雨のような異常気象が増えている。ヨーロッパはもともと、降水量が少ない前提の営農スタイルですから、雨が降ると大きなトラクターが埋まってしまい、使えなくなるんです。すると、適期作業ができなくなり、収穫量が激減してしまうケースも。かといって人をもっと雇って小型トラクターでやるのも無理、となると無人トラクターに関心が集まるというわけです。
――省力化・効率化は世界共通の課題と言えそうですね。それでは野口教授が注目する農業ロボットをいくつか紹介してもらいましょう。
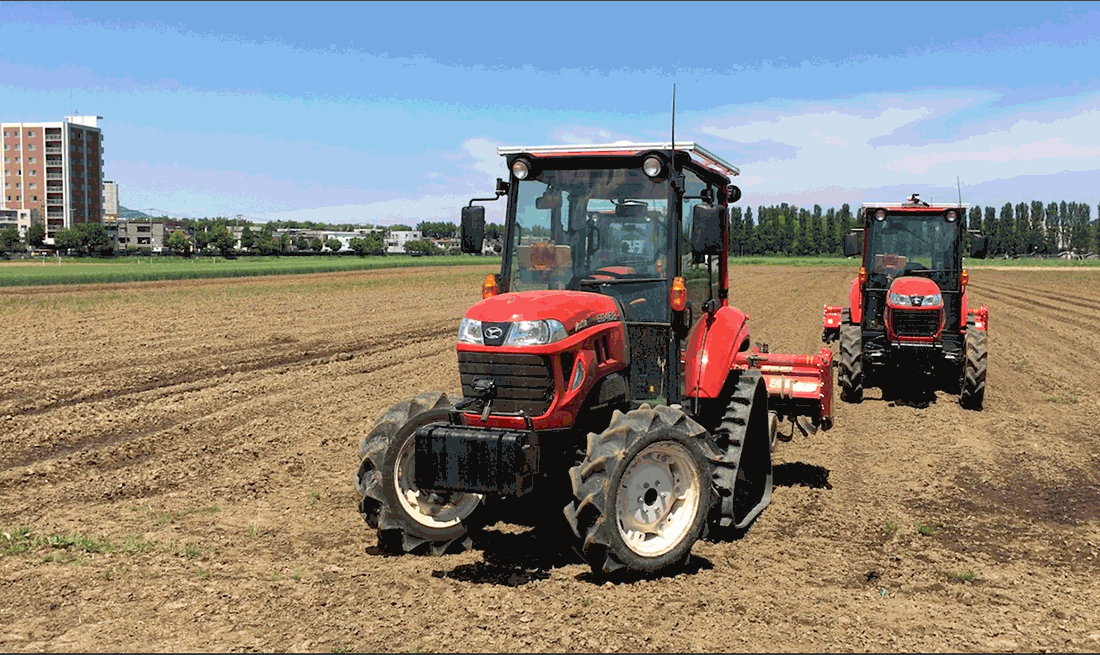
いま、うちの研究室で開発している「マルチロボット」という協調型のロボットは、何台でも一緒になって協調して走ることができます。一台の無人機を大きくするのではなく、複数の無人機を数で調整していくという新しい発想です。何台でも一緒になって走ることができます。市場投入される随伴型のもう少し先の技術ですね。
※協調型ロボットは北海道大学でのデモンストレーションを取材してます。後編をお楽しみに!
宇都宮大学や農研機構が開発しているイチゴ収穫ロボットは、色を相対識別することにより、イチゴの塾度と茎の節谷値を正確に認識し、果実に触れずに収穫できる技術です。イチゴは人の手に触れると傷んでしまうので、果実に触れないことで商品価値を損なわない利点もあります。省力化、生産性向上の点では、夜間に走行させて、翌朝に収穫できていないものを人がチェックすることも可能になりますよね。
農業の場合は、硬い床材ではなく不安定な土のうえで作業するので、人型ロボットは非常に難しい。しかし人型とまではいきませんが、最近はアシストスーツが流行っています。モーターがついていて、持ち上げる作業などがラクにできるというもので、見た目にも非常にユニークです。果実など、重たい収穫物を運ぶ用途のほか、介護現場でも期待されていますね。市販も近いうちに始まるようです。
英・ハーパーアダムス大学のサイモン・ブラックモア教授の講演から。雑草の除去をする無人ロボットで、作物を避けながら除草してます。ウネとウネの間の除草は比較的簡単ですが、作物と作物の間の除草は非常に難しい。機械自体へのプログラムと、カメラによる認識がなせる業ですね。発展させて、レーザーを使って除草をするロボットも研究されています。雑草の成長点をレーザーで焼き切る。究極的には農薬がいらなくなるかもしれません。
農業ロボットについて、研究の第一人者・野口伸教授へのインタビューをお送りしました。野口教授と研究の関わりから、その必要性と現在地、また、農業や社会に与える価値をあらためて確認できました。
お話はまだまだ続きます。次回は、野口教授が現在行っている実証実験の現場をレポート。さらに農業ロボットが実現する、未来の農業についても語っていただきました。



2016年にヤンマーアグリ事業が受賞した4つの賞にフォーカスし、各施策担当者にコメントを伺いました。現場の声を通じ、アグリ事業の「今」と「未来」への取り組みを明らかにしていきます。

ヤンマー、コニカミノルタをはじめとする5社により結成されたコンソーシアムが進めた、農業リモートセンシングを利用した米栽培の最適化。その開発や実証実験の結果など、プロジェクトの全貌に迫ります。