建設機械の電動化の背景と動向について
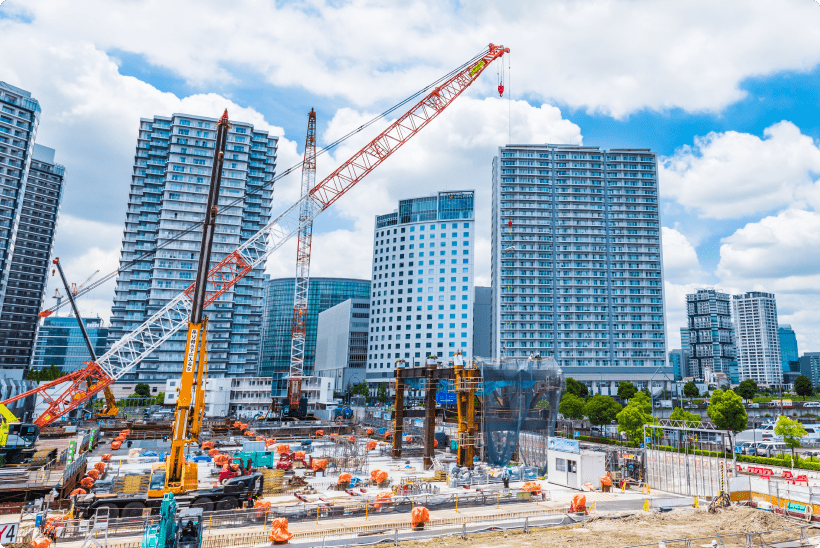
建設業界でもカーボンニュートラルの波が押し寄せ、建設機械の電動化が進展しています。本記事では、この動きの背景とメリット、政策支援、最新の電動建機の種類、そして充電インフラの課題まで幅広く建設現場の未来を形作る電動化の動向を解説します。さらに、ヤンマーパワーテクノロジーが提供する先進的な電動化ソリューションにも焦点を当てていきます。
建設機械の電動化の背景とメリット
まず、建設機械の電動化の背景と、それによってもたらされるメリットについて解説していきます。

建設機械の電動化が進みつつある背景には、CO2排出削減の重要性が増したことと、技術の進化によって電動化の実用性と経済性が向上したことが挙げられます。
近年は地球温暖化対策として、CO2を削減しゼロエミッションを達成するといった動きが顕著になっており、世界中で具体的な目標設定が行われています。日本でも政府が2020年に、社会全体における温室ガスの排出をゼロにする「カーボンニュートラル」の達成を2050年に目指すと発表しています。
この目標を達成するには、電力分野や産業分野を始め、輸送分野、家庭分野などあらゆる所で脱炭素に向けた取り組みを行う必要があり、建設機械においても対策が求められています。国土交通省の調査によると、建設機械自体が出すCO2は令和3年時点で年間571万トンであり、産業部門全体のCO2排出量のうち1.4%を占めると報告されています。全体から見ると大きな割合ではないものの、無視できない量のCO2が排出されているため、その対策として建設機械の電動化に焦点が当たっています。
このように、建設機械の電動化はCO2削減に大きなインパクトを与えることが分かっていますが、近年になって実用化が進みはじめたのは、電動化技術の進化とバッテリーの価格低下が要因です。まず、建設機械は扱うパワーが圧倒的に大きく、従来のバッテリーでは十分な性能を出すことができず、さらに過酷な環境で使われるといった問題もあり、これまでは対応できるバッテリーが準備できませんでした。
しかし、近年になって、バッテリー性能が急速に進化したため、電動建機の実現性が大きく高まりました。また、電動モーター等の効率向上や制御技術の進化も進んだことから、電動建機の性能は実用に耐えられるレベルまで向上しつつあり、実際に製品化も始まっています。
さらに、バッテリー価格は車体価格に占める割合が大きいですが、大量生産によってバッテリーコストは年々低下しており、今後はコスト面での競争力も高くなると期待されます。
CO2削減の必要性から進んでいる建設機械の電動化ですが、従来の製品と比べてメリットが得られるという側面もあります。特に重要な電動建機のメリットを3つ紹介します。
電動建機の一つ目のメリットは、排ガスを全く出さない点です。エンジン駆動の建設機械は5年~10年単位で厳しくなる排ガス規制により、大気汚染物質の排出はかなり減ってきておりますが、周囲への影響を完全になくすことはできません。しかし、電動建機であれば全く排ガスを出さないので、作業者に与える健康への影響を気にする必要が無くなります。今までは排煙対応が必要であった屋内作業や閉鎖空間であっても問題なく使用できるので、建機の活躍の幅が広がります。
電動化による作業精度の向上も見逃せないメリットです。近年では建設機械のICT化が進んでおり、自動で運転するマシンコントロールや、手動操作を補正するマシンガイダンスなど建設機械を自動制御する機能が様々なメーカーから開発されています。これらの機能を使えば人の操作よりも効率的に作業を行えますが、エンジンの振動によるブレが作業精度に影響するといった問題がありました。
一方、電動化であれば振動が発生しない分、自動制御の精度がより向上するといったメリットが得られます。また、電動建機は同じ電気を使うセンシング技術との親和性も高いので、ICT建機を作る上では電動化の方が付加価値をつけやすくなります。
都市部での工事を行う際は、建機が生み出す騒音が少ないのも大きなメリットとなります。建設機械のエンジン音は非常に大きいため、特に夜間作業や住宅地近くで作業を行うときは、騒音が問題となりがちです。一方、電動建機であればエンジン音が存在しないので、周囲に与える騒音を大きく低減できます。地域住民との良好な関係構築に貢献できるほか、作業者への負担も減らせるでしょう。
政策による建設機械電動化の後押し
電動建機には導入メリットもありますが、現状は黎明期であり性能・価格上のデメリットが多いので、開発を加速させるために世界中で政策による電動化の後押しが行われています。ここからは日本を中心に、どのような政策が実施されているかを紹介します。

日本では、2023年10月に設立された「GX建設機械認定制度」において、電動化の推進が行われています。国土交通省が担当しており、バッテリー式、もしくは有線式の電動ショベルとホイールローダー、ホイールクレーンを対象に「GX建機」の型式認証を行う内容となっています。2023年12月には初めての認定が行われ、4社15型式の電動ショベルが認定されており、今後も認証機種が増えていくと予測されています。
なお、GX建設機械認定制度自体は認定ラベルが付けられるだけの内容ですが、GX建機に認定されるとユーザーが購入時に補助金が受けられるので、メーカーにも間接的なメリットが得られます。また、GX建機の導入自体をカーボンニュートラルへの取り組みとしてアピールできることもあり、既に大企業でもGX建機を導入する動きが進んでいます。さらに、政府の直轄工事にもGX建機が導入され始めており、今後はGX建機に対するニーズが高まっていくと予想されます。
電動化の動きは世界的に進んでおり、特にヨーロッパが先行しています。2025年から2030年にかけて、オスロ、コペンハーゲン、ロンドンなどの主要都市でカーボンニュートラル化が進められ、オランダ全土ではゼロエミッション達成が目標とされています。この流れの中で、都市部の公共工事では電動建機を使用する事業者のみが入札可能という案件も出てきています。
また、政府の支援策も進んでいます。北米のカリフォルニア州やオランダでは補助金プログラムが実施されました。これらの施策は、建設機械の電動化を後押しする重要な役割を果たしています。
これらの補助内容は都度変化しているので、海外で電動建機を扱う場合は動向をチェックしておくことが重要です。ヤンマーパワーテクノロジーでは常に海外の動向を把握しているため、気になる方はぜひお問い合わせください。
現在の電動建設機械の種類
建設機械の電動化は種類を問わず開発が行われていますが、現在では限られた地域と種類でのみ実用化が進んでいます。ここでは、電動化が進んでいる欧州と中国市場での主な開発状況を解説します。

欧州市場での電動建機の中で最も実用化が進んでいるのはミニショベルです。現在の電動建機は後方小旋回といった搭載制約から来るバッテリー容量不足が大きな課題ですが、ミニショベルは必要なパワーが小さく、バッテリー容量の小ささが問題になりにくいです。また、ミニショベルは屋内などの狭い空間で使われることが多いので、排気ガスや騒音の無さなど、電動建機のメリットが活かされやすいといった理由もあり、既に一定の使用実績があります。
中国市場では、電動ホイルローダーの実用化が最も進んでおり、特に中・大型機械の中国国内販売が盛んに行われています。市場規模も2023年に5000台を超えており、電動産業用機械市場では世界最大の規模となっており、中国メーカーが市場を寡占している状態です。
充電インフラの現状と課題
このように、今後は電動建機の普及が進んでいくと考えられますが、電動建機を使う上では充電インフラの不足が問題となりがちです。電動建機において充電インフラは必須ですが、現状では建設機械専用の充電設備は整備されていません。さらに、建設機械は山間部や郊外など都会から離れた場所で使われることが多いので、インフラ整備には大きな困難が伴います。
他にも、電力供給の安定性や容量の問題、充電方式の互換性など課題は多いので、安定的に電動建機を利用する環境が整うには時間がかかるでしょう。なお、まだ実現には遠いですが、ワイヤレス充電や、充電による時間のロスをなくして常に建設機械が稼働できる理想的な充電インフラの研究も盛んに行われています。目先のソリューションとしては、可搬式充電器により充電インフラの不備を補う方法が、最も現実的でしょう。
ヤンマーパワーテクノロジーの建設機械電動化ソリューション
ヤンマーパワーテクノロジーでは、100年以上にわたる産業用機械向けパワートレインのノウハウと、バッテリー技術を組み合わせることで、OEMの電動化戦略を一貫して支援する包括的なソリューションを提供しています。グループ会社のHIMOINSA社が可搬式バッテリーシステム「EHR」の販売も行っており、OEMの要望に合わせて企画段階から充電ソリューションを含めたアフターサービスまでのトータルサポートが行えます。そのため、電動建機の開発におけるハードルが下がるに加え、標準化したプラットフォームを活用することで開発期間の大幅な短縮も実現できます。もちろんバッテリー単体の提供など部分的なサポートも可能なので、電動建機の開発で課題を感じている方は、ぜひヤンマーパワーテクノロジーにご連絡ください。